EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

建設業における新リース会計基準の適用は、会計処理に大きな影響を生じさせる可能性があります。工事の際にさまざまな建設用の資材や機械を賃借しているためです。同業界の皆さまにとって参考になるよう、新リース会計基準の主なポイントや実務上の課題について解説します。
本稿の執筆者
EY新日本有限責任監査法人 建設セクター 公認会計士 仙名 良一
建設セクター執行メンバー。主に建設業、不動産業を中心に上場会社や上場準備会社の監査業務に従事。雑誌への寄稿、書籍執筆などにも携わっている。事業会社のシステムエンジニアを経て、当法人入社。入社後は監査部門に所属。
要点
- 建設業では工事の際にさまざまな建設用の資材や機械を賃借しているため、リースの識別およびリース期間の見積りが大きな論点である。
- 建設現場サイドでリースの識別やリース期間の見積り等を行う場合には業務フローの標準化といった実務上の課題がある。
- 建設JVにおけるリースの会計処理も実務上の重要なポイントである。
Ⅰ はじめに
本稿では、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下、本会計基準)、企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下、本適用指針。また、「本会計基準」と合わせて以下、新リース会計基準)、ならびに関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告および移管指針の改正を前提として、新リース会計基準が建設業へ及ぼす影響について解説します。
また、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りします。
Ⅱ 建設業の特色
建設業では工事のために仮設材、照明・配線機器、給排水機器、ユニットハウス、クレーン、ブルドーザーなどさまざまな建設用の資材や機械(以下、資機材)が必要です。自社で所有する資機材を使用する場合もありますが、その多くが賃借されています。元請会社が現場ごとに直接賃借する場合もあれば、協力会社へ工事の一部を発注し、協力会社が資機材を賃借して施工する場合もあります。また、単独で工事を行うだけでなく、民法上の組合を組成して共同出資を行い、他社と共同で施工するケース(以下、建設JV)があり、その場合には建設JVが権利主体となって資機材を賃借し、共同出資者それぞれが出資割合に応じてその費用を負担する場合もあります。
さらに、発注形態もさまざまであり、賃貸借契約書のような法的形式により明確にリース※1と判断できる場合のほか、「資機材一式」等、一定単位の資機材をまとめて発注することにより、賃借の有無やその対象となる個々の資機材が明確に分からない場合もあります。加えて、賃借期間も書面では明確に取り決められていない場合もあります。
このため、本会計基準の適用に当たり、とりわけリースの識別およびリース期間の見積りが建設業特有の大きな論点になると考えられます。
Ⅲ 現行リース会計基準における会計処理の取扱い
現行リース会計基準、すなわち企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」においては、契約がリースであるか、またはリースを含んでいるかの判定につき明確な定めがないため、リースに該当するかの判断が企業によって異なるケースや、単に法的形式(リース契約、賃貸借契約、レンタル契約など)のみで判断するケースが実務上存在していると考えられます。
特に、建設業における資機材については、発注書や注文書、契約書など発注形態は取引ごとにさまざまであるため、実務上は法的形式により判断し、発注書や注文書等により発注されているものはリース取引として識別されていないケースも少なくないと考えられます。実際にリース契約書の締結など法的形式により明確にリースと判断できるようなものは少なく、また、リースと判断できるものであっても解約可能な取引が多く、ファイナンス・リースとして資産計上またはオペレーティング・リースとして注記されている資機材は多くないと考えられます。
以上のとおり、現行のリース会計基準では、資機材はリースとして識別されていなかったり、リースとして識別されていても資産計上されているものは少ないと考えられるため、本会計基準の適用により建設業の会計処理に大きな影響が生じる可能性があります(<表1>参照)。
表1 借手におけるリースの会計処理のイメージ
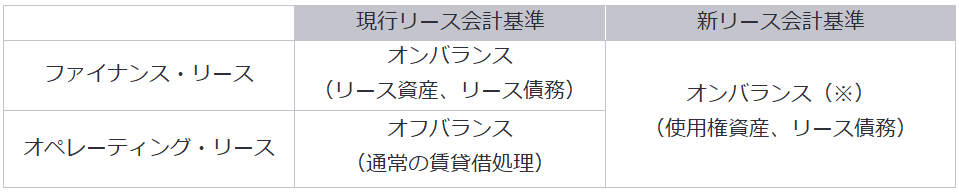
Ⅳ 建設業における新リース会計基準適用上の主なポイント
1. リースの識別
第Ⅱ章のとおり、建設現場では多くの資機材が賃借されています。元請会社が直接リース会社等から資機材を賃借する場合のほか、協力会社へ資機材の賃借を前提とした施工業務を発注することにより資機材の賃借と施工業務の区分が不明確な場合も想定されます。新リース会計基準では、最初にリースの識別の判断が必要となるため、リースの識別が問題となります。
リースの識別の判断に当たって、本会計基準第26項では「契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む」とされています。つまり、リースの識別には、(1)資産の特定および(2)特定された資産の使用の支配、という2つの要件を検討することが必要です(<表2>参照)。
表2 リースの識別の検討事項

EY新日本作成
(1) 資産の特定
まず、資産の特定について、本適用指針第6項は「資産は、通常は契約に明記されることにより特定される」とされています。しかし、建設業の場合、資機材の発注書等の書面では資産が明確に特定できないことも想定されます。ここで、本適用指針BC10項では、国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下、IFRS第16号)の定めおよびこれに関する設例を取り入れていない旨が示されていますが※2、その理由として「当該定めを置かなくとも、顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し、かつ、顧客が当該資産の使用を指図する権利を有している場合には、資産が契約に明記されていなくとも事実と状況によりリースが含まれることが明らかであるときがあり、このときにはリースの識別に関する適切な判断がなされると考えられるためである」としていることから、黙示的に資産が特定されることもあり得ると考えられます。
よって、発注書等の書面では資産が特定できない場合であったとしても、通常は建設現場に搬入された時に必要とする資機材の種類および数量が明確化されるため、黙示的に特定される場合も多いと考えられます。
ただし、前述により資産が特定されたとしても貸主が資産の実質的な入替権を有する場合※3や資産が稼働能力の一部分であり物理的に別個のものと区分できない場合にはリースの識別の要件を満たしません(本適用指針第6項、第7項)。一方、貸主に実質的な入替権がなく、物理的に区分できる資産であればこの要件を満たすことになります。貸主の実質的な入替権については、「例えば、顧客はサプライヤーが資産を入れ替えることを妨げることができず、かつ、サプライヤーが代替資産を容易に利用可能であるか又は合理的な期間内に調達できる場合等がある」とされています(本適用指針BC11項)。通常、工事で使用中の資機材を貸主が入れ替えることは困難であり、借主である建設会社がその入れ替えを妨げることができない場合はかなり限定的な状況と想定されるため、貸主が実質的な入替権を有すると判断されることは少ないと考えられます。また、資機材はそれぞれ物理的に別個の資産として識別できるものが多く、物理的に区分できない場合も限定的と考えられます。
(2) 特定された資産の使用の支配
特定された資産の使用の支配については、その使用期間全体を通じて①顧客が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有していること、および②顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有していること、の2つの要件を満たすことが必要です(本適用指針第5項)。
1つ目の要件である➀については、借主である建設会社が賃借した資機材を使用して工事を進めることができるため、その使用による経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を借主が有していると考えられます。
次の➁については、本適用指針BC13項は「使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る意思決定を考慮する」と示しています。建設会社は施工計画や工事の進捗(しんちょく)状況に応じて、建設現場において賃借している資機材の使用時期や使用時間等、その使用から得られる経済的利益に影響を与える事項の決定権を有していることが多く、この点を踏まえると、基本的には借主である建設会社がその使用を指図する権利を有していると考えられます。
以上のことから、一般的には建設現場において賃借する資機材はリースに該当することが多いと考えられますが、契約条件やその実態に応じて慎重に判断する必要があります。
また、協力会社へ資機材の賃借を前提とした施工業務を委託する場合には、当該施工業務に含まれる賃借が実態としてリースに該当しないか検討する必要があります。すなわち、形式的には協力会社へ施工業務を委託することになりますが、実態として元請会社が対象となる資機材を賃借し、協力会社にそれを使用した作業を委託したと解される取引の場合には、元請会社においてリースに該当する可能性があります。協力会社への発注は発注書や注文書、賃貸借契約書などさまざまな形式で行われるため、取引実態から適切にリースを識別することに留意が必要です。
2. リース期間
本会計基準において、借手のリース期間とは、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間、および借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間の両方を加えた期間であるとされています(本会計基準第31項)。
建設業においては、第Ⅱ章のとおり、リースの範囲に含まれる対象物件の種類は多岐にわたります。また、それらのリース期間については、明確に取り決められていない場合も多く、月次などで使用の都度利用料を支払い、現場で使用しなくなったら返却して賃借が終了するといった、建設業特有の商慣習により、リース期間の見積りが困難な場合が多いと想定されます。このような状況においてリース期間の見積りは、建設現場において使用される資機材等の種類に応じて行うことが1つの方法として考えられます。
例えば、大型重機など金額的にも単独で重要であるものは個別に見積りを行う一方で、現場事務所やコピー機などの物品、および資機材置き場用土地等は、工事の期間にわたり使用することが想定されるため、工事期間をリース期間とすることが考えられます。
なお、一つ一つはそれほど大きくないさまざまな資機材については、過去の実績等に基づき全体の工事期間のどの程度の期間を賃借するかの見積りを行った結果、リース期間は1年以内として短期リース※4に該当すると判断される場合もあると考えられます。
3. 割引率
リース負債は、リース料総額に対して割引計算を行うことで算定されます。借手がリース負債の現在価値の算定のために用いる割引率は、貸手の計算利子率を知り得る場合、当該利率によることとされています(本適用指針第37項(1))。しかし、必ずしも「リース契約」の形式ではなく、発注書や注文書の形式で取引が行われることが多い建設業においては、貸手の計算利子率を知り得ることは多くないと想定されます。このような場合は、借手の追加借入利子率を用いることになります(本適用指針第37項(2))。
4. 非リース部分
リース料の中には、リースの対象となる資機材を賃借することに対する対価のほかに、当該資機材を利用した施工業務に対する人件費などが含まれる場合があります。このように資機材を賃借することに対する対価以外の施工業務などのサービスを受けることに対する対価はリースを構成しない部分、すなわち非リース部分となります。
本会計基準においては、リースを構成する部分とリースを構成しない部分は原則として分けて会計処理を行うとされています(本会計基準第28項)。しかし、「資機材一式」の形式で発注したり請求書を入手したりする場合には、取引の中に非リース部分が含まれているか明確ではない、または非リース部分が含まれていることを把握できたとしても、当該部分の金額を把握できないこともあり得ると考えられます。このような場合には、対応する資機材を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと、または性質および企業の営業における用途が類似する資機材のグループごとに、リース料総額から非リース部分を除外せず、全額をリース料として取扱い割引計算を行うことでリース負債を算定することができます(本会計基準第29項)。ただし、非リース部分を除外する場合と比較してリース負債の金額が増加することについては留意が必要です。
また、協力会社が資機材を調達し施工業務を行う場合には、当該状況が資機材のリースおよび施工サービスを提供する取引なのか、または、協力会社が施工サービスのみを提供する取引であってリースを含まないサービス提供取引なのかは、第Ⅳ章「1.リースの識別」に照らして慎重に判断する必要があります。
5. 減価償却
建設業においてリースの対象となる資機材は、通常は所有権が借手に移転することは想定されません。この場合、リースに係る使用権資産の減価償却費は、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして、定額法等により減価償却費を算定します(本会計基準第38項)(<表3>参照)。
表3 使用権資産の減価償却について

Ⅴ 建設業における実務上の課題
1. 各現場主導で発生する取引
ここでは、建設業において本会計基準を適用する上での実務上の課題について解説します。
まず、建設現場主導で資機材が調達されることに関する課題があります。資機材は多種類かつ大量であることが多く、また、何がリースに該当し、その賃借期間はいつからいつまでかを把握できるわけでは必ずしもない発注書の形式で行われることも多くあります。さらに、協力会社へ資機材の使用を前提とした施工業務の委託として行われることもあります。このような状況において、取引の中にリースが含まれるかを判断し、リースに該当すると判断されるものに対してはリース期間の見積りを誰(どの部署)が行うかは実務上の課題です。建設現場の担当者は、自身の現場の状況を最も適切に把握していると考えられることから、一義的には当該担当者がリースの判定およびリース期間の見積りを行うことが想定されます。この場合、多数の建設現場の担当者がおのおの異なる目線で当該判定や見積りを行うことがないよう、業務フローを標準化することで、建設現場主導で会計処理に必要な情報の整理とデータ化を行える社内体制を整える必要があります(<表4>参照)。
表4 実務上の課題

EY新日本作成
2. 実行予算への影響
第Ⅲ章で述べたとおり、現状は建設現場における資機材の多くは発生時に費用処理されていると考えられますが、リースとして使用権資産が計上された場合、原則としてリース料総額が減価償却費および支払利息として各会計期間に配分されることになります。例えば、毎月定額の月額使用料が定められている資機材であれば、発生時に費用処理していた場合には、毎月定額の費用(外注費や賃借料等)が計上されますが、リースとして使用権資産を計上する場合には、原則として減価償却費と支払利息が計上されます。減価償却費は減価償却方法により各期間の費用配分額は異なり、また、定額法を採用した場合でも利息相当額が調整されるため、毎月定額の費用を計上していた場合とは費用配分額が異なることになります。さらに、支払利息は金融費用であるため、損益計算書における計上区分は減価償却費と異なります。つまり、本会計基準の適用により工事原価の金額が異なることになるのです。
ここで、建設業における工事は一定期間にわたり履行義務が充足されるとして、工事の進捗度に応じて収益を認識している場合が多く(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第38項、第41項)、また、工事の進捗度については原価比例法(企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第161-2項)を採用している会社も多いと考えられます。この場合、工事原価総額(以下、実行予算)を見積もる必要があります。このため、原則的には実行予算策定段階からリース取引に該当する発注を選定し、各期の減価償却費と利息費用を試算し、その影響を反映させる必要があります。従って、本会計基準の適用により、工事利益率が変動し、減価償却方法によっても各期の費用配分額が異なる場合もあるため、原価比例法を採用している場合には収益の計上額にも影響が生じるなど、業績に影響が生じる可能性もあります。
一方、資機材の賃借は一定の期間を通して定額の取引が多いと想定されるため、実務上は、減価償却方法は定額法を採用することも多いと考えられ(第Ⅳ章 「5. 減価償却」)、前述のとおり利息相当額の分だけ従来と費用処理金額が異なります。支払利息については重要性が乏しいとして、利息相当額を計上しない(本適用指針第40項(1))または工事原価総額の見積りでは考慮しないことも実務上は想定されますが、その場合には個々の工事のみの影響だけでなく、個々の工事の影響額を積み上げた上で、財務諸表全体として重要性が乏しいと言えるか留意が必要です。建設業は年度によって受注量が大きく変動する場合もあり、各工事の発注タイミングによってもリース取引量が変動しますので重要性の判断は慎重に行う必要があります(<表4>参照)。
なお、資機材の賃借は大型重機やハウスといった比較的多額かつ長期のものから仮設材や発電機等の少額または短期のものまで多種類あり、少額リースや短期リースに該当するものも多いと考えられるため、会社によってはその影響が小さい可能性もあります(<表5>参照)。
表5 少額リース、短期リースの会計処理の概要

EY新日本作成
Ⅵ 関連するその他の会計上の論点
建設JV
建設JVにおいては出資割合の最も大きい構成員が、通常、JVの代表者として選定され、この代表者のことをスポンサー、それ以外の構成員をサブといいます。建設JVでは、重要事項についてはJV運営委員会の協議により決定されますが、スポンサーがJV実行予算の策定や資機材の調達先の決定、施工管理などに対して大きな影響力を有します。
ここで、スポンサーとサブでそれぞれリースの識別に留意が必要です。建設JVの権利義務は最終的にその構成員に帰属するため、通常、スポンサーとサブは出資の割合に応じて責任を負うことになります。このため、リース取引に関する権利義務もそれぞれの出資割合に応じて有すると考えられます。この点に鑑みれば、スポンサーとサブはそれぞれの出資割合に応じた使用権資産を計上することになると想定されます。
しかし、前述の処理を行うには、実務上の課題があります。サブがリースの会計処理を行うためには必要な情報をスポンサーから入手する必要がありますが、一般的に建設JVの会計処理はスポンサーの帳簿内で行われ、サブはスポンサーから契約書や請求書などの証憑(しょうひょう)ではなく、取下げや外注費等の報告資料により自らの会計処理を行っています。このため、サブがリースの会計処理を行うためにはスポンサーから新たにリースの会計処理に必要な情報をすべて入手しなければなりませんが、それはスポンサーにとって過大な負担となり、また、建設JV内での情報管理体制の見直しが必要になるなど、実務上の大きな影響が生じる可能性があります。
他方、スポンサーは建設JVの代表者として契約の締結や財産の管理等を行う権限を有する場合もあり、また、資機材の発注、施工管理等に大きな影響力を有していることからリース対象となる資機材の選定や使用時期、使用方法についても大きな影響力を有していることも多いと言えます。このため、スポンサーおよびサブのリースの識別の検討に当たっては、リース取引の契約関係やスポンサーの権限、影響力をどのように評価するか、特に「特定された資産の使用の支配」(第Ⅳ章 「1. リースの識別」(2))の検討には留意が必要と考えられます。
Ⅶ おわりに
建設現場では賃借する資機材が大量かつ多種類あり、その発注形態もさまざまであるため、特にリースの識別やリース期間の見積りには慎重な判断が必要であり、会計処理に当たっては割引計算や減価償却が必要になるなど、業務負担は避けられないと考えられます。また、支払利息や減価償却費によっては業績に大きな影響が生じる可能性があります。加えて、使用権資産とリース負債の計上により総資産や負債が大きく増加する場合もあり、これらに伴い、ROIC(投下資本利益率)やROE(自己資本利益率)、自己資本比率等の重要な経営指標にも影響が生じる可能性があります。
このように、建設業でも新リース会計基準の適用により業務負担や会計処理、業績、重要な経営指標に大きな影響が生じる可能性がありますので、会計基準への理解を深め、その影響を把握し、早期に業務プロセスを整える必要があると言えるでしょう。
サマリー
建設業では工事の際にさまざまな建設用の資材や機械を賃借しているため、新リース会計基準の適用は会計処理に大きな影響を生じさせる可能性があります。皆さまの参考になるよう、建設業における新リース会計基準の主なポイントや実務上の課題について解説します。
関連コンテンツのご紹介
EY新日本有限責任監査法人より、会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。
業種別の会計の基礎について、コラム記事を掲載しています。
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。
情報センサー
EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。




